はじめに:読書に「わたし」を求めた理由
こんばんは。さちです。
今回は読書のカテゴリです。少し長くなりますが、最後まで読んでいただけたら嬉しいです。
私が読書をしはじめたのは高校1年生です。
近くに友達がいないという理由で、1人の時間が増えたのが大きいです。
読書の世界に自分の居場所を求めたのです。
読書は一人でする行為であり、その時間は本と自分だけの世界。
他者の考えは介入せず、自分の内側から生まれる感覚に触れられる——
その瞬間、「わたし」という存在が肯定されるように感じます。
『こころ』を今、読み直して
実際に読んだ本の中で影響を受けた数冊のうち、今回は夏目漱石の『こころ』について書きたいと思います。
『こころ』は多くの学生が教育の中で触れることがある作品です。私も初めて読んだのは高校の授業でした。
私が衝撃を受けたのは、Kの自殺が本筋ではなかったという点です。
当時は「なぜKが自殺したのか」「先生はそれをどう受け止めたのか」を中心に考えていました。
しかし今読み返すと、全編を通して問うべきはむしろ「なぜ先生が自殺したのか」だと感じます。
その理由は、①先生の孤独感、②現実で存在することの否定——この二つが深く関係していると考えます。
孤独のはじまり:裏切りと失望
先生の孤独感は、人を信じられなくなったことから生まれます。
初めに先生は叔父に裏切られます。信用していた叔父が、父の遺産を誤魔化して使っていたのです。先生はこう語ります。
私は人に欺かれたのです。しかも血のつづいた親戚のものから欺かれたのです。(中略)私は死ぬまでそれを忘れることができないんだから。
このとき先生は叔父を恨むばかりで、自分が悪人ではないと考えていました。
しかし「自分も悪人である」と自覚する行為をしてしまうのです。それは親友であるKを裏切る行為です。
罪と葛藤:Kを裏切る先生
ひとつ目はKからお嬢さんが好きだと打ち明けられたとき。先生は心の中である策略をめぐらせます。
Kが理想と現実のあいだに彷徨してふらふらしているのを発見した私は、ただ一打ちで彼を倒すことができるだろうという点にばかり目をつけました。(中略)私はまず『精神的に向上心のないものはばかだ』と言い放ちました。
この発言は、かつてK自身が口にした言葉でもあります。先生はKの信念を逆手に取り、Kの恋の行手を封じようとしたのです。それは先生自身の恋を優先させるための戦略的言動で、あまりに人間的な行為でした。
ふたつ目に、お嬢さんの母(以下奥さん)に縁談を持ちかけるという行動にでます。その後、Kを出し抜いたことへの良心の呵責に苛まれます。しかしKに事を打ち明けるのは自分の狡猾さを露呈することでもあります。
私の良心がまたそれを許すべきはずはなかったのですから。
要するに私は正直な道を歩くつもりで、つい足をすべらしたばかものでした。もしくは狡猾な男でした。(中略)しかし立ち直って、もう一歩前へ踏み出そうとするには、今すべった事をぜひとも周囲の人に知られなければならない窮境に陥ったのです。私はあくまですべった事を隠したがりました。
先生の良心と自尊心との間で葛藤が生まれたのがこの瞬間だと感じます。
奥さんが語ったKの反応
そうこうしているうちに、奥さんからKにお嬢さんと先生との縁談話が伝わってしまうのです。先生はその時の様子を奥さんから聞きます。
Kはこの最後の打撃を、最もおちついた驚きをもって迎えたらしいのです。(中略)最初はそうですかとただ一口いっただけだったそうです。しかし奥さんが「あなたも喜んでください」と述べた時、彼ははじめて奥さんの顔を見て微笑をもらしながら、「おめでとうございます」といったまま席をたったそうです。
このKの反応には、絶望とも諦念ともつかない静けさが漂っています。先生はその話を聞き、自身の小ささと醜さをさらに感じることになったのです。
「おれは策略で勝っても人間としては負けたのだ」という感じが私の胸に渦巻いて起こりました。(中略)しかしいまさらKの前にでて、恥を掻かせられるのは、私の自尊心にとって大いな苦痛でした。
ここでも先生の自尊心とKに事を伝える良心との間での葛藤が見られます。さらには先生が自己を卑下している点も見られます。
ついに打ち明けようと決心した夜、Kは自殺してしまいます。先生は葛藤から決心したのにも関わらず、その機会を失ってしまう結果となったのです。
自己否定へ:叔父と自分の重なり
Kの自殺を経て、先生はあることに気づきます。
叔父に欺かれた当時の私は、(中略)ひとを悪くとるだけあって、自分はまだ確かな気がしていました。(中略)それがKのためにみごとに破壊されてしまって、自分もあの叔父と同じ人間だと認識した時、私は急にふらふらしました。
ここで先生は、恨んでいた叔父と自分が同じ存在であると悟ります。先生を欺き財産を手に入れた叔父=Kを欺きお嬢さんを手に入れた先生です。
そして人間というものが「善悪で単純に分けられるものではなく、状況次第で誰もが悪に染まる」と帰結します。その認識が先生をさらに追い詰めました。
私はただ人間の罪というものを深く感じたのです。(中略)自分で自分を鞭うつよりも、自分で自分を殺すべきだという考えが起こります。私はしかたがないから、死んだ気で生きて行こうと決心しました。
こうして先生は、罪悪感と孤独の中で”生きていることそのもの”を否定していき、明治天皇の崩御と乃木大将の殉死をきっかけに自殺します。
孤独と生への執着
しかし、先生は根底から生きることに対して完全な無気力になったのか疑問に思いました。それは先生が鎌倉で出会った青年へ向けた遺書の言葉からです。
私の過去をあなたのために物語りたかったのです。
私は今自分で自分の心臓を破って、その血をあなたの顔に浴びせかけようとしているのです。私の鼓動がとまった時、あなたの胸に新しい命が宿ることができるなら満足です。
記憶して下さい。私はこんな風にして生きて来たのです。
ここに見えるのは、死への絶望ではなく、生きてきた証を残そうとする意志。自分を理解してほしいという願いと、記憶してほしいという切実な祈りが滲んでいると感じます。
孤独とは空っぽの状態ではなく、実際は誰よりも求め、欲しているのだと思います。先生は、自分を理解してくれるかもしれない青年に、遺書を通じて心を打ち明けたのです。
結びに:孤独とともに生きる
夏目漱石の『こころ』は、孤独が人を死に追い詰めるという現実を描きながらも、同時に「孤独を受け止めることで生きる力を見出す」作品であると感じます。
孤独は確かに人を苦しめる。けれど、孤独を通して自分の内側と向き合うことは、生きることそのものの意味を取り戻すことでもあるのだと思います。
では、また次の投稿で。
出典:夏目漱石『こころ』(角川文庫)
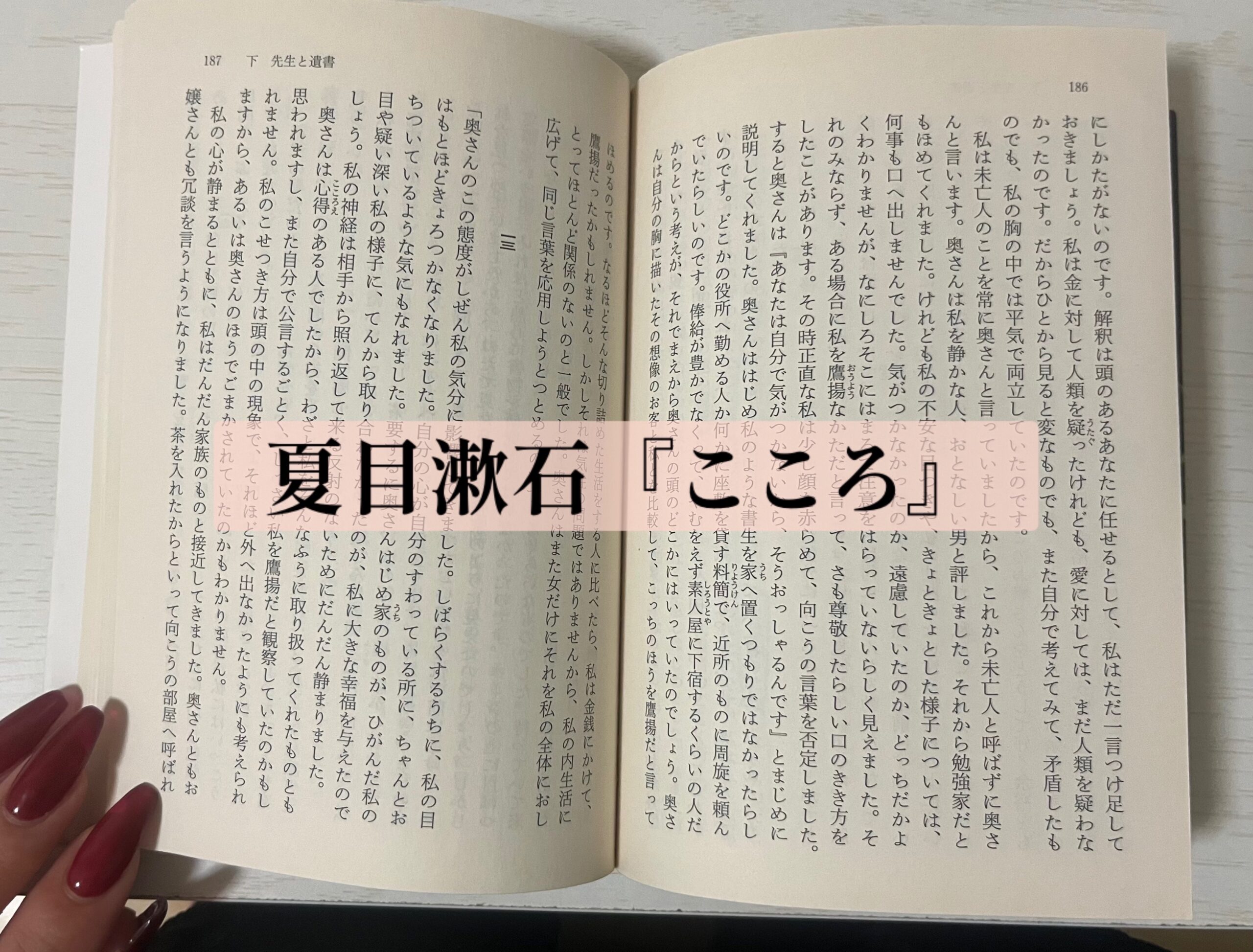


コメント